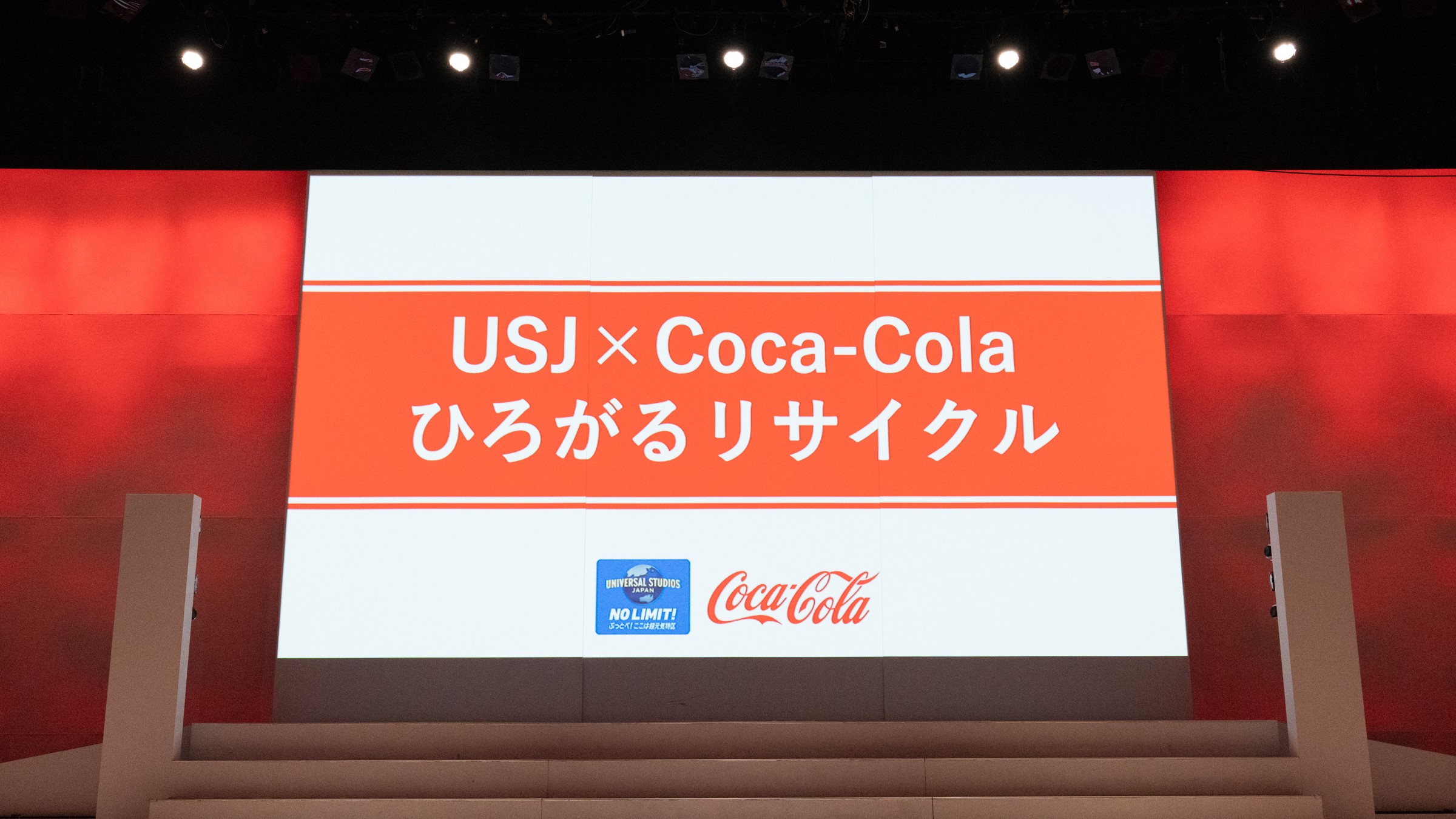コーポレートブログ

すべては“知ること、聞くこと”から。LGBTQ+当事者の課題解決を通じて東由紀が目指す「誰もが自分らしく働ける社会」
2025年11月20日

まだ「LGBTQ+」という言葉もほとんど知られていない時代から、LGBTQ+当事者が職場で直面する課題を改善する活動をアライ(※)として続けてきた東由紀(コカ・コーラ ボトラーズジャパン 執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長)。
現在は一人ひとりが自分らしく働くことができるインクルーシブな環境を実現すべく、あらゆる取り組みを牽引しています。
2025年10月1日に日本コカ・コーラ本社で開かれた、LGBTQ+当事者への理解を深めるための映画『息子と呼ぶ日まで』鑑賞会とトークセッションにも東は参加し、取り組みへの思いを語りました。
この記事では10月のイベントの模様をお伝えするとともに、「アライとは支援者でも理解者でもなく“共感し、ともに活動する仲間”」「誰もが誰かのアライになれる」と発信し続ける東の信念をお届けします。
(※)「同盟」や「味方」などを意味する英語「ally」が語源で、自分自身が性的マイノリティであるかどうかによらず、差別や偏見をなくす社会の実現を目指し行動する人のこと
「当事者はいない」という思い込みがSOGIハラスメントにつながる
2025年10月1日、日本コカ・コーラ本社において、LGBTQ+当事者への理解を深めるための映画鑑賞会とトークセッションが開催されました。テーマは「インクルージョン」。参加者が当たり前と思っていた価値観を少し揺らし、「知る・考える」きっかけをつくる時間として企画されたものです。
冒頭はLGBTQ+の当事者を取り巻く現況や基本的な知識として、性のあり方を構成する4つの要素について話を受けました。
・性的指向……どのような人に性的関心が向くか、向かないか
・性自認……自分の性別を自分でどう認識しているか
・性的特徴……法律上の性別が割り当てられる特徴
・性別表現……服装や仕草、言葉づかいなど

NPO法人プライドハウス東京 代表理事 五十嵐 ゆりさん
このうち性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字を取った総称は「SOGI」(ソジ)と呼ばれ、性的指向や性自認に関連して職場で発生する差別的言動・行動や嫌がらせなどは「SOGIハラスメント」と呼ばれています。
「人口のおよそ3〜10%がLGBTQ+に該当すると言われています。これは日本におけるAB型の人や左利きの人とほぼ同じ割合です。一方、職場で自身が当事者であることを公表していない人は60〜70%に上るという調査もあります。『うちの職場に当事者はいない』という思い込みは、SOGIハラスメントにつながりかねません」と指摘しました。
イベントでの上映作品は、トランスジェンダーの日常をテーマにした短編映画『息子と呼ぶ日まで』。上映後は監督の黒川鮎美さん、主演俳優でありトランスジェンダー当事者の合田貴将さん、そして当社からは東が加わり、制作背景や当事者としてのリアルな思いを語り合いました。
主演の合田さんは「男性として就職活動をするか、女性として行うか、その段階から悩んでいました」と、自身の学生時代を振り返ります。当時はカミングアウトをせず、女性の姿で活動していた合田さんですが、内定先企業の先輩に勇気を出してトランスジェンダーであることを打ち明けたといいます。その企業の人事部は合田さんの意向を確認した上で「男性として入社してください」と伝え、配属先の支店では全員がLGBTQ+アライのステッカーを貼って合田さんを迎えました。

主演俳優 合田 貴将さん
その現場で研修を担当していたのが、当時同じ企業に勤務し、ダイバーシティ推進を担当していた東でした。「現場の支店長の強い希望でLGBTQ+の理解を深める研修を行い、アライを表明したい人にステッカーを配布しました」と語ります。
その経験から東は「制度を作るときは、『当社にはカミングアウトしている人がいないから必要ない』ではなく、人口の3~10%はLGBTQ+であるという統計値から『当社にも当事者がいる』という前提で設計することが大切です」と強調しました。なお、現在東は、当社においてホルモン療法費用の補助施策や性別移行休暇の導入、性別を限定しないユニフォームの採用など、制度と文化の両面から多様性を支える取り組みを推進しています。

誰も驚かず、特別視もしない。多様性を受け入れるアメリカでの原体験
東は個人として、LGBTQ+の方々が職場で直面する課題を改善する活動をアライとして続け、当社においても性的マイノリティであるかどうかにかかわらず、誰もがハッピーに働ける職場づくりを目指して活動する「LGBTQ+&アライ従業員ネットワーク」のスポンサーとして貢献してきました。
そんな東の活動の出発点は、海外で過ごした学生時代にさかのぼります。
東が初めてLGBTQ+当事者と出会ったのは、アメリカの大学に通っていた頃でした。仲の良い友人グループの1人の男性が「Himを連れてくる」と言って恋人を紹介した場面を、今でも鮮明に覚えているといいます。
「その場にいた全員が自然に受け入れていたんです。誰も驚かず、特別視もしない。あのときの空気が、私の追いかける多様性の原点でした」

当時の体験を語る東
日本に帰国してから勤めた外資系企業では、上司が同性愛者であることを公表していたり、性別移行を済ませた同僚がいたりと、多様であることが当たり前に感じる環境で働いていました。しかし、その会社が日系企業に買収されたことをきっかけに転機が訪れます。
「新しく加わった組織で、人事部門から突然『LGBTQの社内ネットワークのリーダーになってくれませんか』と声がかかったんです。当時、社内にはカミングアウトしている当事者が1人もいないと言われ、『2万人も社員がいるのにそれはおかしい』と強い違和感を覚え、1人もカミングアウトをしていない原因はマジョリティ側の課題なのではないかと考えるようになりました」
「知ること」が常に出発点、「理解したつもり」にならないことが大切
「知ること」が常に出発点、「理解したつもり」にならないことが大切
2010年頃、まだ“LGBTQ”という言葉さえほとんど知られていなかった時代。東は「マジョリティ側を変える」ことを自分の使命とし、活動を始めます。しかし、最初から自信を持って進めたわけではありませんでした。
「周囲には当事者の方もいましたが、当時の私はLGBTQ+について正しい知識を持っていませんでした。どんな言葉が差別的なのか、何を言ってはいけないのかも分からなかった。だから、リーダーを引き受けたものの、“学びながらやるしかない”という状態でした」

最初の頃は、間違ったことを言って傷つけてしまうのではないかという不安が大きく、当事者と話すことさえ怖かったといいます。それでも一歩ずつ向き合い続けたのは、当事者からの率直な言葉があったからでした。
「ある当事者に『何を差別的と感じるかは人それぞれなので、怖がらずに聞いてほしい。もし不快に感じることがあれば、その思いを素直に伝えるから』と言ってもらって救われました。それ以来、当事者と接する際には”不快に感じることを言ってしまったら教えてほしい“、”答えにくかったら答えなくていいから”と前置きして話すようにしています」
こうして東は、当事者の声を聞きながら知識を積み重ねていきました。
「ただ、どんなに知識が増えても、学び続けなければならないことには変わりありません。知ることが常に出発点であり、理解したつもりにならないことが大切だと感じます。たとえばトランスジェンダー当事者である合田さんのストーリーを知っても、別の当事者の背景や課題はまったく異なるでしょう。だからこそ、聞く姿勢を常に忘れないようにしています」

アライは支援者でも理解者でもなく“共感し、ともに活動する仲間”
東は、人事としての立場から、社内外で「誰もが誰かのアライになれる」と伝えています。
「私はLGBTQ+の課題を通じて話していますが、これはすべての人の働きやすさにつながる活動です。たとえば、私自身も女性であり、社内ではジェンダー的にマイノリティ。同じように誰もが、何らかの場面でマイノリティとなる経験をしたことがあるはずです。だからこそ、誰もが安心して働ける環境をつくりたいと思っています」

当社では、性別移行休暇制度の導入やホルモン治療への費用補助など、制度面でも先進的な取り組みを進めています。これらの制度もLGBTQ+当事者だけを対象にしたものではなく、生理不順や更年期障害の症状軽減のためのホルモン治療にも適応し、誰もが活用できる形に整えました。「制度を作って終わりではなく、職場内でLGBTQ+への理解をさらに広げ、円滑に運用できるようにすることが大切」だと東は語ります。
一方、東はアライ活動を「強制すること」にも警鐘を鳴らします。
「社内独自で『アライ検定』のような取り組みを実施することや、『全員でアライのステッカーを必ず貼ってください』と呼びかけるような活動には、私は反対です。アライを表明したくないと思っている人に強制してしまうと、当事者は誰に相談すればいいのか分からなくなってしまうからです」
そして、東は“アライ”という言葉の意味そのものについても、誤解が多いと指摘します。
「アライは支援者でも理解者でもありません。支援という言葉の裏には、“助けてあげる側”守る側”という上下関係が生まれてしまう。それは、マジョリティが作り上げた社会構造を前提にした考え方です。
私は、アライとは“共感”し、ともに活動する仲間”だと考えています。アライという言葉はもともと英語で”同盟”を意味します。つまり、対等な関係であり、ともにこの社会を良くしていこうという姿勢そのものなんです」。
大切なのは、知らないことを認め、学び続けようとする姿勢なのだと、東はもう一度強調しました。
「アライとは、知ろうとする人であり、行動しようとする人が集まるネットワーク。だからこそ、ただ数を増やすことよりも、一人ひとりが自分の意思で考え、ともに歩もうとすることが何より大切なのだと思います」

※記載された情報は、公開日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。