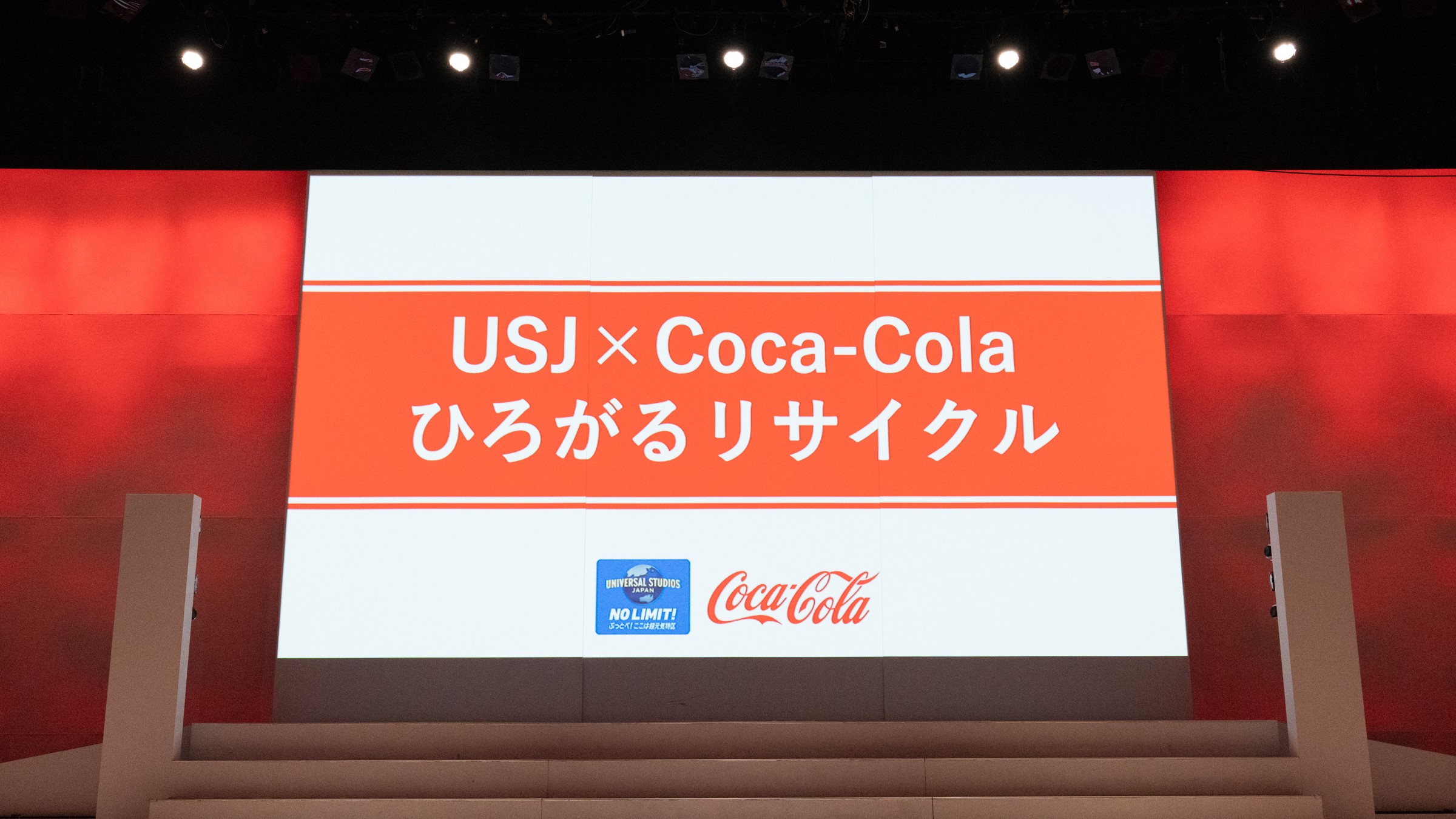コーポレートブログ

万博で得た知見をサステナブルな未来につなげる。コカ・コーラ ボトラーズジャパン 大阪・関西万博総括【後編】
2025年10月6日

大阪・関西万博は、半年間にわたり世界中の人々が集い、大盛況となりました。当社は「前編記事」でご紹介した取り組みの他、シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」での活動、「水素カートリッジ式発電自販機」の開発・設置、PETボトルの水平リサイクル推進という大きな取り組みにも挑みました。これらの取り組みは大阪・関西万博の掲げる「SDGs達成への貢献」とも親和性の高いものです。
壮大なメッセージ性を持つパビリオンの認知拡大や生物多様性保全に向けた生態系データ収集、富士電機と世界で初めて開発した「水素カートリッジ式発電自販機」の実証、そして日本型資源循環モデルを世界に発信する水平リサイクルの活動。いずれも制約や困難を抱えながらも、多様な協業先と社員が力を合わせてやり遂げた挑戦であり、サステナブルな未来に向けた確かな一歩を刻むものとなりました。
シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」:一般市民も巻き込んだ生態系データ収集プロジェクト

河森正治氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」に、当社はゴールドパートナーとして参画しました。主に担当したのは、パビリオンの認知拡大と生態系データ収集プロジェクト「いきもの探しはデカルチャー」の推進という二つの大きな役割です。
取り組みを主導した西村広二は「パビリオンは生物多様性がテーマで、壮大な物語性と未来へのメッセージが込められており、開幕前にどのように認知拡大を図るかが課題でした」と振り返ります。
「そこで、当社や協賛企業が取り組む具体的なサスティナビリティ領域の活動事例を組み合わせ、より身近に感じてもらえるよう発信方法を工夫しました。また、「コカ・コーラ」のブランド力を生かした発信も実施しました」(西村)
いきものコレクションアプリ「バイオーム」を用いた生態系データ収集プロジェクトは、一般市民を巻き込み、森や緑地、海などで楽しみながら多くのデータを集める取り組みとなっています。
「協業先であるTOPPANやくら寿司と共同で展開した『いきもの探しはデカルチャー』では、全国規模でデータ収集が広がり、300万を超えるデータが集まっております(※)。また、社内においても、コンテストやイベントを開催し、多くの社員に「生物多様性」というテーマを自分ごととして認識する機会を提供しました。社員エンゲージメント向上にも繋がったと考えています」(西村)※2025年7月末時点
「いきもの探しはデカルチャー」ウェブサイト:https://shojikawamori.jp/expo2025/biome_quest/

また、未来共創プログラムの一環として、当社京都工場の見学や大山工場水源域でのコカ・コーラ「森に学ぼう」プロジェクト、他社が手がけるビオトープや養殖場体験などを実施し、多くの人々が自然や生物多様性を学ぶ機会を提供しました。
西村は「大阪・関西万博に対して、開幕前にはやや否定的なトーンの報道もありました。しかし協賛企業とともに成功を信じて活動し続けた結果、開幕後には来場者がSNSで肯定的に発信してくれるようになり、会場の空気が一気に変わっていくのを実感できました」と手応えを語ります。
大阪・関西万博という舞台での露出は、当社にとっては単なる広告ではなく、社会にサステナビリティのメッセージを伝える重要な役割を果たしたのです。

水素カートリッジ式発電自販機:次世代型自動販売機の開発
当社は大阪・関西万博の場で、水素をエネルギー源とする次世代型自動販売機の稼働を実証しました。背景には、温暖化対策と脱炭素社会の実現に向けた業界全体の課題がありました。
「当社の一般的な自動販売機では、2005年比でCO2排出量を約60%削減していましたが、2013年以降は改善が停滞していました。そこからさらに進化させるためには、根本的な技術革新が必要でした。水素は安定供給が可能でスペース効率も良く、自動販売機との親和性が高い。清涼飲料業界のリーディングカンパニーとして挑戦する意義があったのです」

開発に携わった空増知尚は、取り組みに込めた思いをそう語ります。
開発にあたっては、富士電機との協業により省エネ性能を向上させ、水素カートリッジの交換を容易にする工夫を導入しました。また、現場でのオペレーション負担を軽減することを重視し、安全性にも配慮した設計を行いました。

しかし実際の運用では、販売量や気温の変動により出力が安定しない場面もありました。「そのたびに現場で調整を繰り返し、柔軟に対応できる方法を探りました」と空増は振り返ります。
「大阪・関西万博という特殊で厳しい条件のもとで稼働させたことは、実証実験として極めて有意義でした。販売データや電力供給データをリアルタイムで可視化することで課題を把握し、次世代機の開発に役立つ知見を数多く蓄積することができました。

水素に限らず、環境に配慮した技術を開発し続けることが重要です。大阪・関西万博で得た経験を糧に、これからも清涼飲料業界の未来を切り拓いていきます」(空増)

「水素カートリッジ式発電自販機」設置式:https://www.ccbji.co.jp/wp_blog/hydrogen-vending-machine/
PETボトル水平リサイクル:日本型資源循環モデルを世界へ
容器リサイクルの分野では、国内同業他社と協働し、PETボトルの水平リサイクル(ボトルtoボトル)を推進しました。これは日本国際博覧会協会が掲げた「グリーンビジョン」に基づく取り組みであり、日本の資源循環型社会の強みを世界に示すものとなりました。

この取り組みを主導した土屋朋彦は、「世界に誇れる資源循環モデルを発信したいと考えていました」と当初の思いを振り返ります。
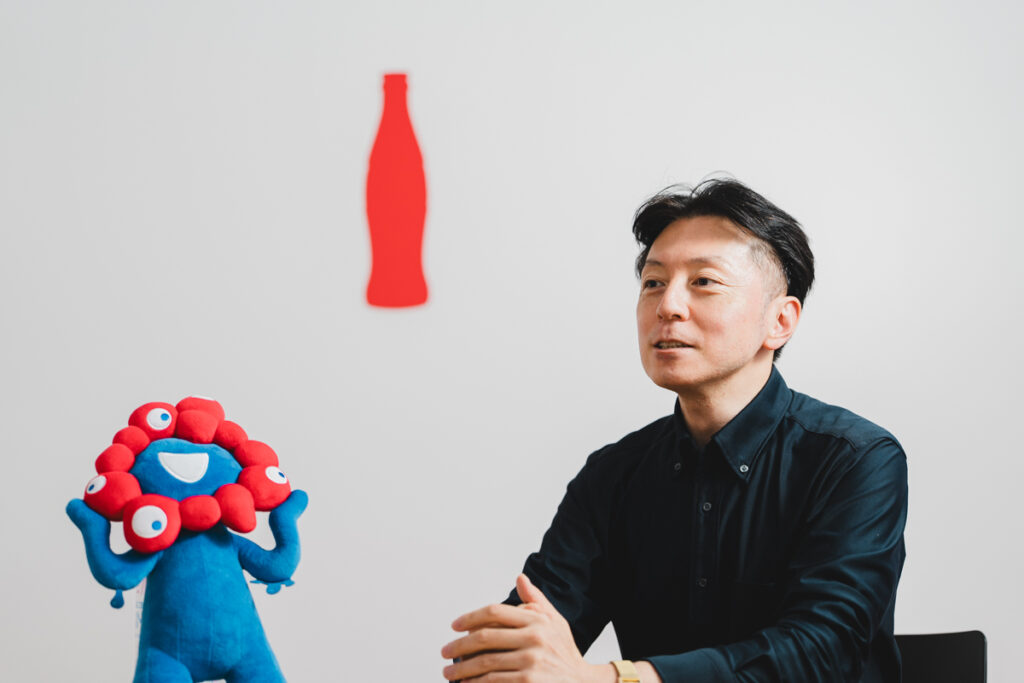
「日本はデポジット制(※)を導入せずとも高いリサイクル率を維持しています。これは世界に誇れる資源循環モデルであり、大阪・関西万博を通じて発信できることに大きな意義がありました。PETボトルはごみではなく資源であるという意識を広め、分別行動を後押ししたいと思っていたんです」(土屋)
※ 飲料を購入する際、製品価格に容器代として上乗せされたデポジット(預かり金)を支払うことで、使用済みの容器を返却した際にデポジットが返金される仕組み
会場内の45カ所に設置された「3Rステーション」を拠点に回収を進めましたが、当初は活動範囲が来場者に分かりにくいという問題も明らかになりました。そのため日本国際博覧会協会と協議し、誘導員が積極的に分別を呼びかけることで適切な回収につなげました。
「回収量は4月10トン、5月13トン、6月19トン、7月31トン(いずれもコカ・コーラ ボトラーズジャパン分)と順調に増加しました。来場者数の増加やイベントとの連動も影響し、分別行動の定着が進んだことが数字に表れたのだと思います」(土屋)

リサイクルボックスのデザインも工夫され、資源循環を啓発するロゴを目立たせることで来場者の意識喚起につながりました。協会や同業他社、リサイクラーからも「残渣が減り歩留まりが改善した」「分別啓発の良い事例となった」と高い評価を得ました。
「大阪・関西万博という世界的な場で、日本型資源循環モデルを発信できたことは大きな成果です。この経験を次につなげ、資源循環型社会の実現に貢献していきたいと考えています」(土屋)
取組み詳細:https://www.ccbji.co.jp/news/detail.php?id=1683
「SDGs達成への貢献」に共鳴した私たちの思い。貴重な財産を手に未来を創る
「コカ・コーラ」というブランドの認知を広げる場だった1970年の日本万国博覧会。55年後の大阪・関西万博では、当社が創造する新たな価値を認知していただく場として、さまざまな施策を推進してきました。
当社の大阪・関西万博施策全体をリードした西村広二はそのように振り返ります。

大阪・関西万博が目指した「SDGs達成への貢献」は、当社のミッションにも深くかかわります。当社の事業活動に付随する社会課題解決の手段として、生物多様性保全に向けた生態系データ収集プロジェクトや、「水素カートリッジ式発電自販機」の開発、資源循環の実証など多様な取り組みを行い、それらを通じて貴重な知見を得ることができました。 また、「前編記事」でご紹介した他企業・協会とのコラボレーションを通じて、未来を担う人材の育成にも大きく貢献できたと考えています。
これらは、大阪・関西万博という特別な場に携わったからこそ得られた経験であり、今後の事業活動の基盤強化につながる重要な財産になると確信しています。
大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。西村は当初、「正直、このテーマを自分ごととして捉えてはいなかった」と話します。
「その頃の私は、近畿エリアのマーケットシェアをいかに上げていくか、どれだけ多く自動販売機を設置するか、飲食店の取引をどのように拡大させるかばかり考えていました。しかし大阪・関西万博に携わったことで、重要なのは決してそれだけではない、いかに社会に貢献していくか、ということを考えるようになりました。
当社のミッションは『すべての人にハッピーなひとときをお届けし、価値を創造します』です。大阪・関西万博での取り組みを通して、私はハッピーの形をたくさん知ることができました。私たちの事業を通して生み出される価値は、ただ飲料を提供するだけではなく、誰かを幸せにするものなんだと確かに目撃することができたんです」(西村)

西村は大阪・関西万博での取り組みを振り返り「私自身の価値観を変えた出来事」と話し、「これから私も自身の役割を通じて、少しでも未来にハッピーをつなげることができるように取り組んでいきたいです」と述べました。
社員一人ひとりの努力と協賛企業・パートナーとの連携によって成果を形にすることができた大阪・関西万博での取り組み。持続可能な未来社会を実験する場で得られた知見と経験は、閉幕後も当社の大切な財産となり、次の挑戦を支える確かな礎となっていくはずです。

※記載された情報は、公開日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。