コーポレートブログ

社員一人ひとりの挑戦がレガシーに。コカ・コーラ ボトラーズジャパン 大阪・関西万博総括【前編】
2025年10月6日

4月13日の開幕から約半年間にわたり、国内外から数多くの来場者を迎えた2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)。当社はこの特別な舞台で、自動販売機のオペレーションや会場内レストラン「ラウンジ&ダイニング」の運営、お得意さまへのホスピタリティプログラムの推進など多彩な施策を展開しました。また、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(日本国際博覧会協会)への社員出向など人材育成にも取り組みました。
社員の挑戦と成長、そして仲間や協力企業との連携によって成し遂げられたこれらの取り組みは、大阪・関西万博という非日常空間で得られた貴重なレガシーとして今後の事業に生かされていくはずです。この記事では取り組みを主導した社員の声とともに、私たちが得た学びや気づきをお届けします。
自動販売機のオペレーション:大阪・関西万博会場内約250台を支えた一元管理体制

大阪・関西万博では、会場内に設置する自動販売機すべてのオペレーションを当社が担いました。会場内約250台、全飲料メーカーの機器を一括して管理するという、前例のないオペレーションに挑んだのです。

担当した大幸亮平は、「『お客さまに常に冷えた商品を提供する』ことを使命とし、各社に納得いただける体制をつくるため、丁寧に時間をかけて調整を進めました」と振り返ります。
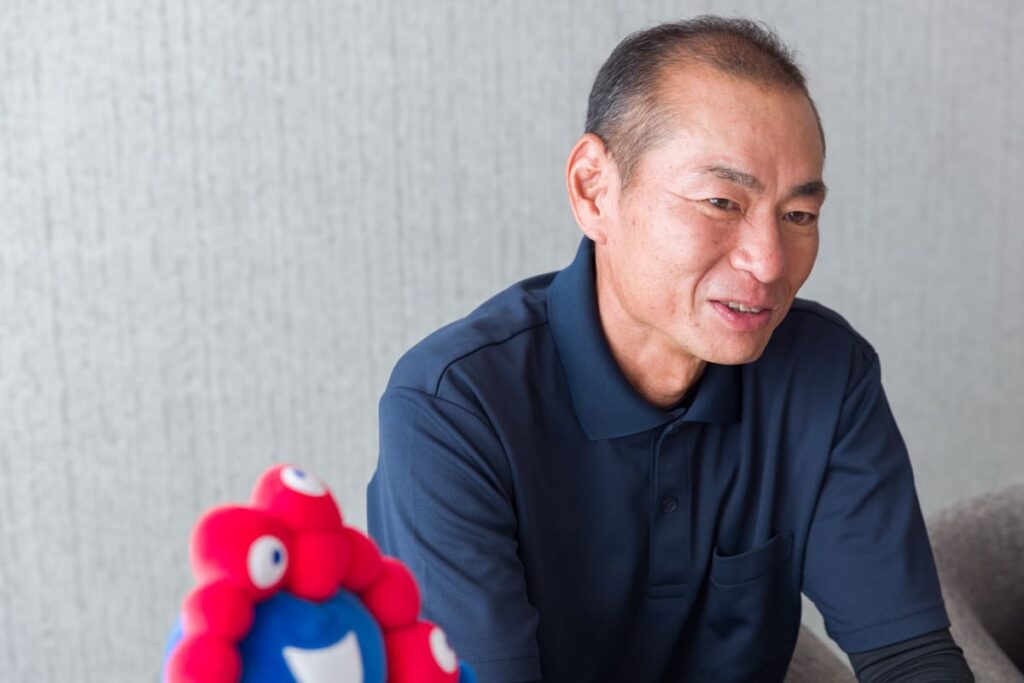
冷蔵倉庫を会場近くに手配し、そこから冷えた商品を配送。補充担当者を配置し、会場を5エリアに区切って効率的な補充体制を築きました。とはいえ、すべてが順風満帆に進んだわけではありません。最大の課題は酷暑でした。
「今年は観測史上最も暑い夏となりました。台車で商品を運び続けるスタッフは、常に熱中症のリスクと隣り合わせです。焦る気持ちを抑え、休憩と体調管理を優先してもらうことを重視しました」(大幸)
当社の事業エリア各地から延べ500名を超えるメンバーが集結し、多様な人材が協力し合う中、熱中症を発症した来場者にスタッフが「アクエリアス」を手渡す場面もあり、自動販売機の存在が「命を守るもの」であることを改めて実感したといいます。

現場で商品補充などオペレーション業務を担った平岡敬人は、自らの信念をこう語ります。
「私は『楽しむこと』をモットーにオペレーションに取り組みました。現場では海外からのお客さまと交流する場面も多く、学びが尽きませんでした。こうした機会を楽しまないのはもったいないという気持ちで臨みました」(平岡)
もちろん、楽しむだけではなく、お客さまをおもてなしする姿勢も大切にしました。「どうすればお客さまにもっとワクワクしていただけるか」を常に意識し、国籍を超えた多様なニーズに対応できるよう努めていたのです。
忘れられない出来事として、平岡は小さな子どもを助けた経験を挙げます。
「補充中に幼いお子さまが近くで転倒しているのを目撃し、すぐに駆け寄って親御さんのもとへ送り届けました。『ありがとう、助かりました』と感謝いただいたことは忘れられません」(平岡)

閉幕を前に平岡が強調したのは、チームワークと誇り、そして自らに訪れた変化です。
「大阪・関西万博では、常にチームで動きました。各地の社員と深く関わることで、これまで以上にコミュニケーションの大切さを実感しました。また、大阪・関西万博ではお客さまと直接コミュニケーションを取れる機会が多く、気持ちよく商品を購入していただくための積極的なアプローチが行えました。この経験から『人柄や思いやりを前面に出した接客』をより深く学べたと感じます」(平岡)
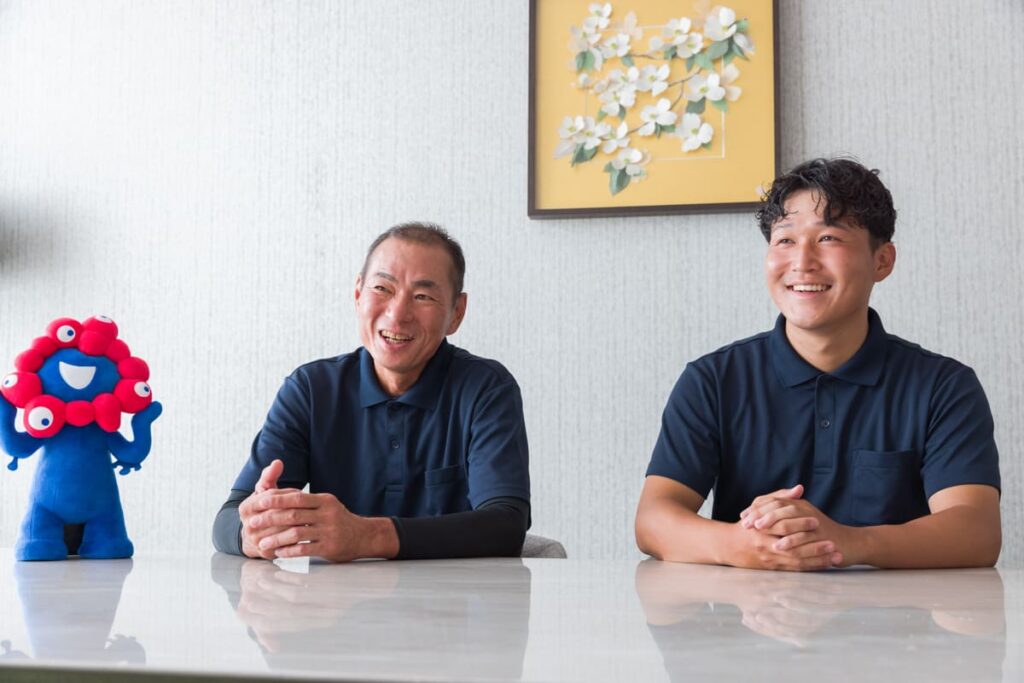
「ラウンジ&ダイニング」:ゼロから挑んだレストラン運営
大阪・関西万博において、当社はレストランの運営に挑戦しました。協業パートナーはロイヤルホールディングス。飲料メーカーとしての枠を超えた、新たな試みでした。

「飲食店向け営業は長く経験してきましたが、ゼロからレストランを立ち上げることは初めてでした。万博という特殊なロケーションでは数々の制約があり、設計・施工から運営まで、未経験の業務に短期間で対応しなければならず、時には夢にまで見るほど課題は山積みでしたね」
担当した小木曽友治は当初の心境を笑いながら振り返ります。
そんな中で支えとなったのは、協業の力でした。「経験豊富な上司や、協働するロイヤルホールディングスのみなさんからアドバイスを得られたことが大きな救いでした」と振り返ります。
苦労して立ち上げた店舗。来店者からの反応は好意的でした。

「設定価格は少し高めでしたが、『大切な人を連れてまた利用したい』という声を多くいただきました。出展者や協賛企業の接遇の場としても活用され、価格以上の価値を感じていただけたと思います」(小木曽)
特に学びとなったのは、ロイヤルホールディングスのホスピタリティだったといいます。
「料理のクオリティが高いことは言うまでもなく、お客さまに対しては、迎え入れる瞬間からお見送りまで、きめ細やかな気配りが徹底されていました。レストラン運営の神髄を学べたのは大きな財産です」(小木曽)
閉幕を前にプロジェクトを振り返り、小木曽は感謝と成長を口にします。
「業務は常に他部署との連携で進み、普段接点のない部署の方とも数多く協働し、物怖じする余裕もない中で積極的に動けました。不安と覚悟を抱きながら走り続けた2年間で、どんなイレギュラーにも対応できる姿勢が身につきました」(小木曽)
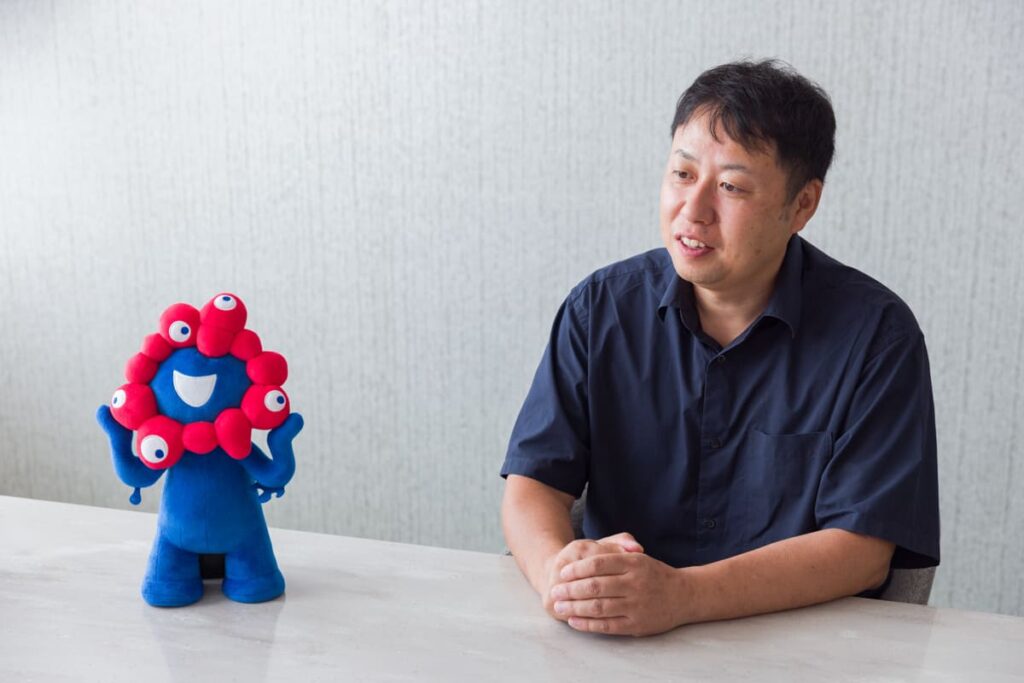
「ラウンジ&ダイニング」店舗詳細:https://www.ccbji.co.jp/wp_blog/lounge-dining-expo/
ホスピタリティプログラム:お得意さまを迎える責任とやりがい
ホスピタリティプログラムは、当社が主要なお得意さまを大阪・関西万博に招き、当社の取り組みを直接ご覧いただきながらブランド体験を共有するために設けた特別な企画です。
「開幕前には当社の営業担当者に説明会を実施し、希望があれば会場ツアーも行いました。資料だけでは分からない動線や雰囲気を体感し、開幕後のお得意さまへの案内に活かせるよう工夫しました」
企画・運営に携わった粟田安李はプログラムに込めた思いをそう語ります。
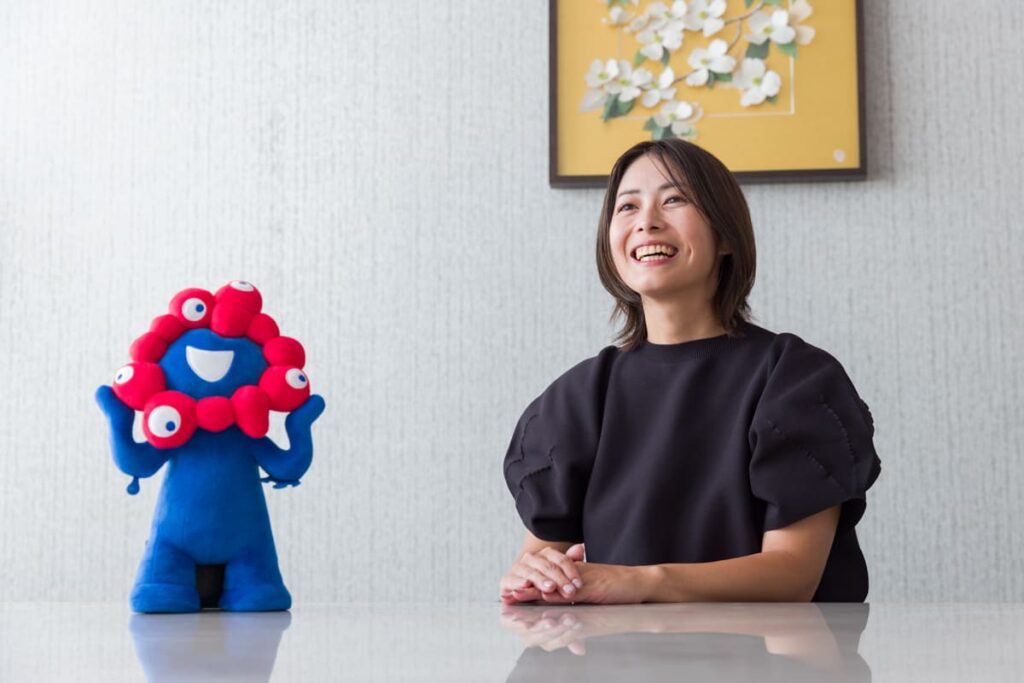
開幕後は200組を超えるお得意さまを迎え入れました。営業担当者から「お得意さまに大変喜んでいただけた」「有意義な時間だった」といった声が多数寄せられ、励みになったといいます。
そんな粟田にとって、この業務は大きな責任を伴うものでした。
「今年から大阪・関西万博のプロジェクトチームに異動し、『ホスピタリティプログラムといえば粟田』と言ってもらえるよう全力を尽くしてきました。至らない点もありましたが、200組を超えるお得意さまを迎えられたのは、高い専門性を持つチームメンバーや営業担当者、協力企業のおかげです。本当に感謝しています」(粟田)
満足度を追求しながら、細心の注意を払いながらやり遂げた業務は、粟田に大きなやりがいをもたらしました。「国家的イベントでコカ・コーラ ボトラーズジャパンとしてホスピタリティプログラムをリードできたことは、今後の社会人生活に生かせる貴重な財産になりました」と振り返ります。

日本国際博覧会協会への出向:異なる環境で得た学びと挑戦
2022年1月から2年5か月間、大場博之は日本国際博覧会協会へ出向し、企画部出展課で協賛制度の企画を担当しました。当時はまだ参加国や出展・協賛企業すら決まっていない状況で、ゼロから制度設計が始まりました。
「まずは企業や団体が大阪・関西万博に参加するためのメニューや協賛特典を企画しました。出展や協賛を決めた企業が増えると、それぞれの企画をサポートし、協会内の部署との橋渡し役を務めました。コカ・コーラ ボトラーズジャパンを含む各企業の万博への参加を促し、参加企業のプレゼンスを高めることが、自分に期待される役割だと感じていました」(大場)
出向中に苦労したのは、異なる文化や意思決定スタイルを持つ多様な企業からの出向者で構成された万博協会内における業務調整だったといいます。
「企業ごとに意思決定のスピードやプロセスが違うため、合意形成には時間がかかりました。同じチームの中でも『前例を重視する人』と『新しい挑戦を重視する人』の間でバランスを取るのは、特に苦労するポイントでした」(大場)
しかし、そこで得られた学びは大きなものでした。
「異なるバックグラウンドを持つ人と議論することで、自分だけでは思いつかない発想が生まれました。相手の価値観を理解して説明した結果、より強い信頼関係を築くこともできました」(大場)
出向後は当社の大阪・関西万博プロジェクトチームに戻り、協会で培った人脈や企画したスキームを活かし、社内のサステナビリティチームや広報チームとの連携を推進。「万博協会出向中の経験は、社内外の橋渡し役としてプロジェクトを推進していくうえで大いに役立ちました」と大場は言います。
「準備段階では不確実性への不安を抱えていましたが、チームで共通の未来像を持ち、成功を信じて進んできたからこそ、今の盛り上がりを見ることができました。協会で築いた人脈や経験は、今後の人生においてもかけがえのない財産です」(大場)

2023年1月から協会のイベント局に出向した倉本幹太郎は、会期前から会期中まで多岐にわたる業務を担当しました。
「私は会期前、14の施設で行われる数千件のイベント調整を担いました。特に開会式や協会主催のドローンショー、花火、大型ライブなどの準備・運営は、大規模イベントならではの緊張感と責任を伴いました。また、イベント予約システムや情報管理アプリの運用、さらにはフェス会場やサウナ施設の管理まで任せていただきました」(倉本)
出向にあたり倉本が意識していたのは、「大阪・関西万博の成功が当社や自分の未来につながる」ということ。
「イベントの企画から運営までを一貫して担い、商品企画や販売戦略に直結する学びを得ました。マネジメント層の出向者からはプロジェクト推進のスキルを、行政関係者からはルールづくりの重要性を学ぶこともできました」(倉本)

協会は民間企業出身者に加え、経済産業省など行政関係者も多く在籍しており、多様な知見が交わる場でした。「誰も正解を知らないテーマに挑む苦労と向き合いながら、それぞれの知見を組み合わせることで大きな成果を出せたと感じます。何より『覚悟を持ってやり切る姿勢』を学べたことが最大の収穫です」と倉本は語ります。
「このプロジェクトは『ゼロからイチを創る』挑戦でした。苦労の連続でしたが、仲間と力を合わせて形にしてきたことはかけがえのない経験です。出向前と比べ、視野も考え方も大きく成長しました。この経験を当社の業務に活かし、次の挑戦へつなげたいです」(倉本)
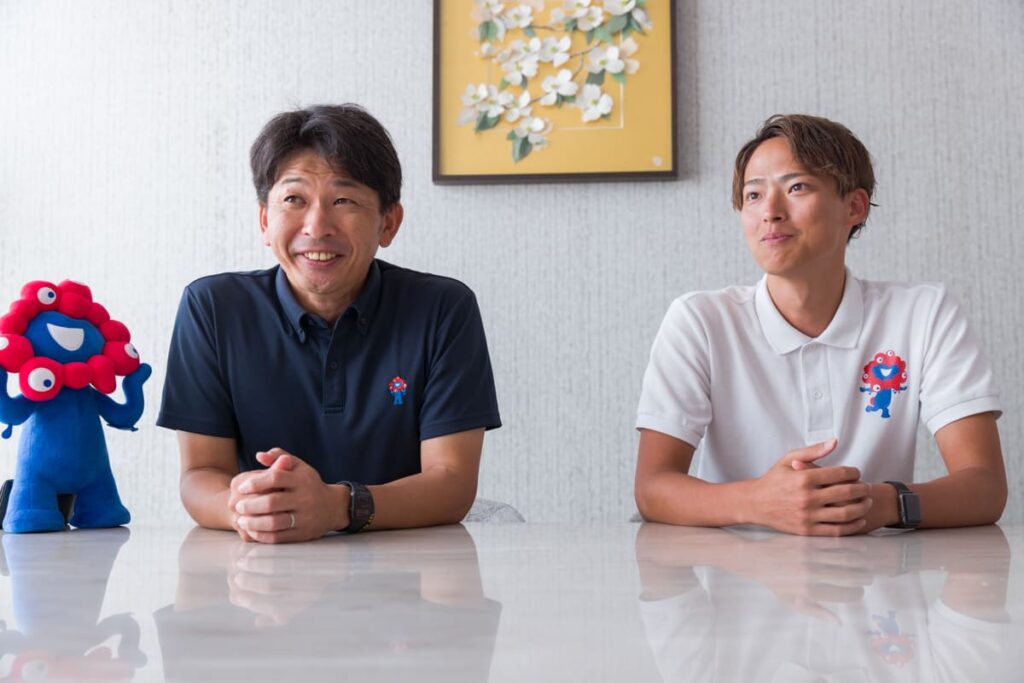
大阪・関西万博における当社の挑戦は、学びと成長の連続でした。酷暑の中で仲間と支え合いながら業務を遂行し、新しい事業領域に挑み、顧客や協力企業と深い絆を築いたことは、すべて未来につながる貴重な財産。社員一人ひとりが誇りを胸に刻んだこの経験は、次の挑戦への確かな原動力となるはずです。
続く【後編記事】では、大阪・関西万博が掲げた「SDGs達成への貢献」とも親和性の高い、サステナブルな未来に向けた当社の挑戦をご紹介します。ぜひ、【後編記事】もあわせてお読みください。

※記載された情報は、公開日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。






