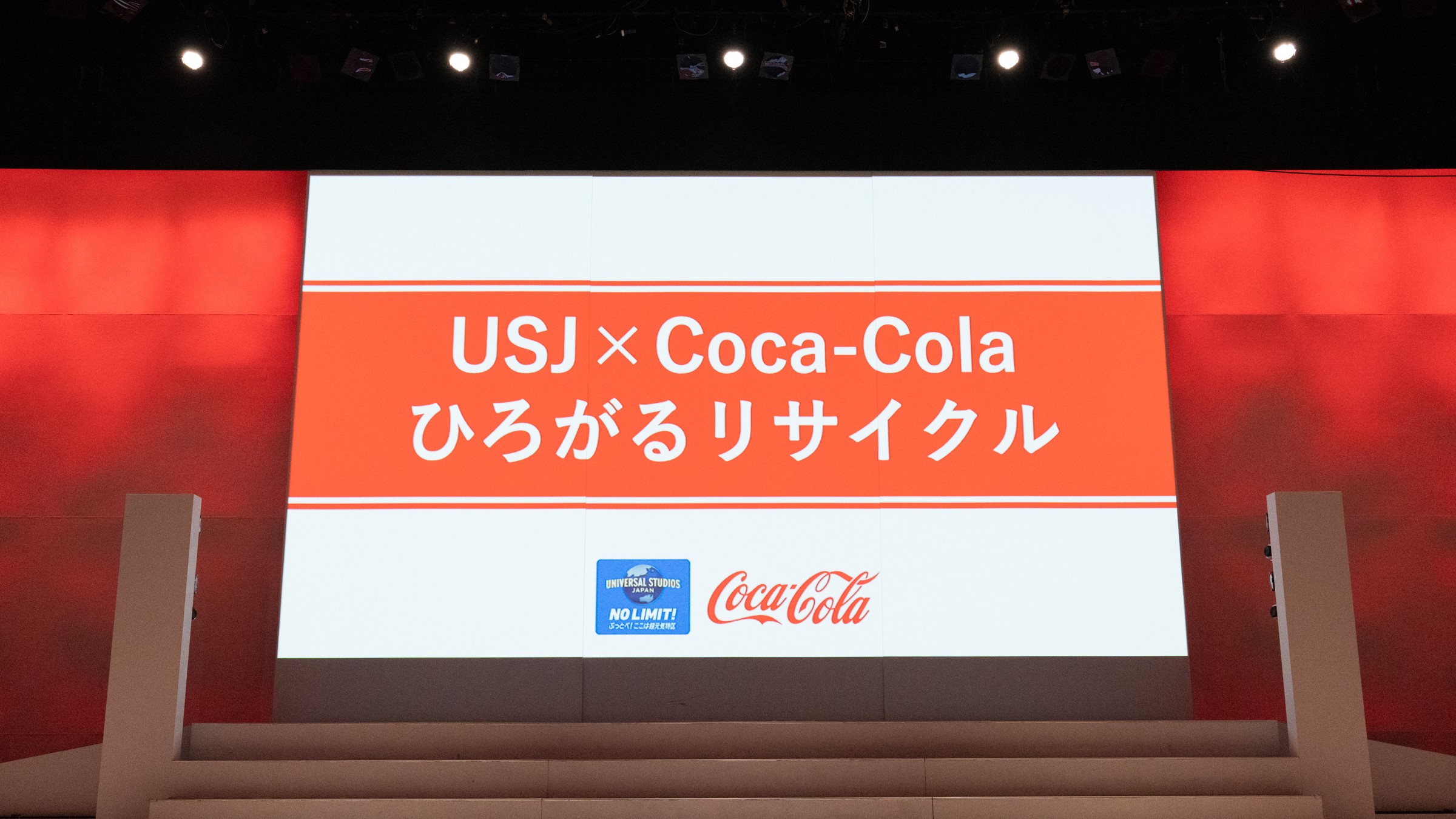コーポレートブログ

日本のコカ・コーラシステム初、国際認証「AWSゴールド」を取得。地域とともに水資源を守る取り組みを加速
2025年10月21日

2024年12月、コカ・コーラ ボトラーズジャパンの白州工場(山梨県北杜市)は、水資源の責任ある利用と管理に関する国際認証であるAWS(Alliance for Water Stewardship)規格の「ゴールド認証」を取得しました。これは日本のコカ・コーラシステムとして初の取得です。
AWSは、2010年に世界自然保護基金(WWF)をはじめとするNGOを中心に設立された、水のサステナビリティを推進するための機関。AWS規格では、事業所に加え、ステークホルダーとの連携を通じた流域全体における水資源管理を促進し、持続可能な水の利用と管理における基準を定めています。
この記事では当社がAWS規格のゴールド認証取得に取り組んだ背景や担当者の思い、そして日本の水資源を守るために企業が向き合うべき課題についてお伝えします。
水は地域社会や文化だけでなく、企業の発展のためにも重要な資源
古来より水資源に恵まれてきた日本では、水に関する問題が顕在化している諸外国と比べて、資源としての「水」を考える意識はまだまだ醸成されていないのかもしれません。それでも近年では、企業や行政による水資源保全の取り組みが活発になっています。
水資源保全は自社だけの課題ではない
コカ・コーラ ボトラーズジャパンでは、サステナビリティ推進1課が中心となり、白州工場(※)のAWSゴールド認証を取得しています。この取り組みの背景を、同課の小澤佳南、樋永久美子、中村綾乃に聞きました。
(※)白州工場は、100%リサイクルPETボトルおよび飲料後に資材分別を簡素化するラベルレスパッケージを採用した「い・ろ・は・す 天然水」を主に製造している工場でもあります。

——なぜコカ・コーラ ボトラーズジャパンはAWS認証取得に挑んだのでしょうか。
小澤:当社では以前より、全世界のコカ・コーラシステム共通の品質・オペレーション管理システム「KORE」(Coca-Cola Operating Requirements)を運用して水資源保全の取り組みを進めてきました。しかし、これはあくまでも自社の仕組みです。AWSは世界的に認められた外部認証ですので、認証を取得することで水資源保全の取り組みを一層広く社会へ伝えられると考えました。
樋永:当社のビジネスにとって水は極めて重要な資源で、工場周辺の水資源は他の企業とも共有しています。その水をしっかり管理していることを、できるだけ多くの方に知っていただく機会にしたいと考えています。
中村:認証取得の過程で、これまで以上に取り組みの幅が広がることにもつながりましたね。AWS規格の要求事項では、集水から排水までの過程にとどまらず、他のステークホルダーとも頻繁に関わる必要があると実感したんです。雨が降って森に蓄積され、地下水になっていくプロセス全体を見据え、関係者と向き合うことが求められていると認識しました。

——水資源保全は自社だけの課題ではないのですね。
樋永:工場がその土地で稼働する際には大量の水を使います。地域社会に不安を与えてしまっては持続可能なビジネスは成り立ちません。水資源を共有する方々との対話を行っていることが、AWS認証の重要な条件の一つとなっています。
中村:集水域全体で水資源の使用量を削減することも重要です。これは私たち自身の課題であると同時に、地域全体の課題でもあると考えています。
地域のステークホルダーに対し、AWSが厳格な外部監査を実施
——どのようにプロジェクトを進めていったのでしょうか。
樋永:2023年12月にプロジェクトを始め、一年後のちょうど12月に認証を取得しました。まず認証取得に向けてキックオフを行い、その後、AWSが定める14時間のトレーニングを工場関係者とサステナビリティチームで受講しました。
小澤:私たちだけではなく、工場のメンバーにも時間を割いて受講してもらいました。主体は工場のメンテナンス課と、地域渉外も行う総務課です。
樋永:工場では普段から水に関するさまざまな検査を実施しています。法令に準拠した検査や、KORE基準による検査結果も集めました。これらのデータを整理し、外部コンサルタントの協力を得ながら資料を準備しました。その上で、地域のステークホルダーの方々からヒアリングも行いました。
——「ステークホルダー」とは、どのような方々を指すのですか?
小澤:自治体や地域住民、近隣の食品工場をはじめとした地元の企業、農家さんはもちろん、洗車サービスを提供するガソリンスタンド、川で釣りをする方々まで、幅広い方々が対象となります。AWS認証に向けた監査プロセスでは、そうした多様なステークホルダーと関わります。
樋永:外部監査では、AWSの監査人が直接ステークホルダーにインタビューします。山梨県と北杜市の自治体関係者にもご協力いただき、当社の取り組みの中で水に関する懸念がないかを確認。ここに企業側は関与できず、AWS認定の監査人が、独立した第三者機関として、厳格な基準で実施します。
小澤:その後の監査では農業関係者から「地域の農業用水路のメンテナンスに関する課題」なども声も寄せられるようになりました。水資源に関わるさまざまな要望に、私たちが耳を傾ける立場になったのだと実感しています。

「地域とつながる工場」の協力があったからこそ認証を取得できた
——認証取得にあたり、特に大変だったことや苦労したことを教えてください。
樋永:AWS認証を取得している企業の前例は国内にまだ少なく、手本となる情報が少ない中での取り組みとなりました。ロールモデルがないため、地域の方々との対話においても最初は理解を得るのに時間がかかるのではないかと感じます。
中村:これまでは水資源管理を軸に地域と対話する機会が少なかったので、「集水域全体で水を保全する」という考えをどのように伝え、共感していただくべきなのかは悩みましたね。
小澤:そうした中で心強かったのは、白州工場のみなさんがとても協力的だったことです。白州工場の総務課マネジャーは以前から地域の祭りに参加するなどして地元と深く関わっており、認証取得に向けて地域の自治会とのコミュニケーションを先頭に立って進めてくれました。工場側の理解と協力体制がなければ、認証取得は実現できなかったと強く感じています。
——AWS認証の中でも「ゴールド」を取得できた理由は?
樋永:当社では数年前からすべての工場で水使用量削減プロジェクトを進めており、単一工場だけでなく、全工場が努力している点も評価されました。白州工場の排水管理においても、法令とKORE基準のより厳しい方に沿って定期的な管理を行い、水質に影響がないことを確認のうえ、河川放流しており、最終的に釜無川へ合流します。
さらに、白州町には「地下水保全・利用対策協議会」があり、20年間活動を続けています。地元企業や有識者、自治体が協力し、地下水のモニタリングを行って地域の生活用水の確保や産業の発展を支えているのです。当社もこの取り組みと連携していることがゴールド取得の大きな要因となりました。

——AWS認証を取得してから、取り組みはどのように進化していますか。
中村:統合報告書やコーポレートサイトを通じて、水資源保全に向けた取り組みの発信を強化しています。国際認証を得たことで、説得力を持って伝えられることの意味は大きいですね。
樋永:当社の取り組みは林野庁がまとめた企業事例としても紹介されました。白州工場の従業員もAWS認証に高い関心を持ち、「日本のコカ・コーラシステム初の取得」であることに誇りを持ってくれているようです。
小澤:日本ではまだまだ、水資源保全の重要性が十分に浸透していない現状もあります。今後も私たちの取り組みをより分かりやすく社会に発信し、水資源の重要性を広く伝えていきたいと考えています。
白州工場でAWS取得後初の定期監査を実施
地域と連携した水資源保全の継続を確認
8月中旬、白州工場にて、AWS認証取得後初となる定期監査が3日間にわたり実施されました。
AWS認証では、認証取得後も年に一度、AWSによる監査が行われます。本年の定期監査では、AWS監査人による現地訪問に加え、社内外のステークホルダーへのインタビューが実施され、認証取得後も地域と連携した水資源保全活動が継続されているかが確認されました。
特に印象的だったのは、地元企業の皆さまにご協力いただいたインタビュー対応です。地域の方々との対話を通じて、水資源保全に関する情報提供や協働の機会を今後も模索していく必要性を、改めて認識する機会となりました。
定期監査においても、白州工場が地域とともに歩む水資源保全の取り組みが、単なる認証取得にとどまらず、継続的な対話と協働によって支えられていることを再確認しました。今後も、地域との信頼関係を大切にしながら、持続可能な水資源管理に取り組んでまいります。


※記載された情報は、公開日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。